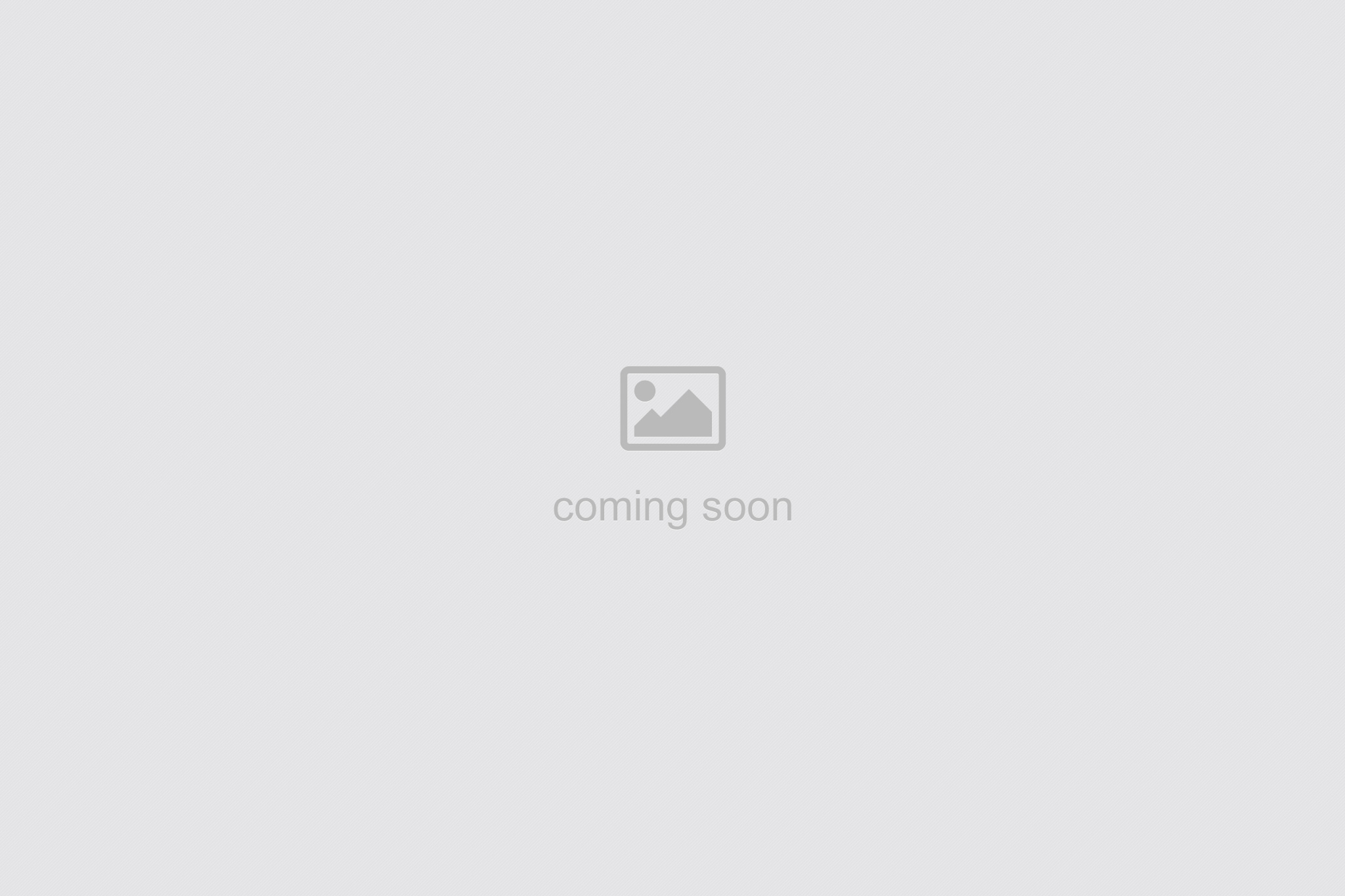確定申告において所得税の寄付金控除の制度を利用することで、所得税を減らすことができます。
寄付金控除の方法として、「税額控除」と「所得控除」の2種類があり、確定申告においていずれか一方を選択することになります。
一般的には「税額控除」を選択した方が「所得控除」よりも減額の効果は大きくなりますが、個人の所得、寄付金額等によって異なりますので、下記の<比較表>をご参照ください。
税額控除と所得控除の比較表 ← 所得税減少額の目安
『税額控除』
寄付金額から2,000円を差引いた金額の40%を所得税額から控除できます。
(例)寄付金が30,000円の場合 課税所得にかかわらず
税金の減少額:(30,000円-2,000円)×40%(※)=11,200円(一部例外を除く)
所得税が11,200円減少し、実質負担額は18,800円(30,000円-11,200円)となります。
(※)大阪府在住の方は府民税の減額分と合わせて42%、大阪市在住の方は更に市民税の減額分を加えて50%となります。所得税の確定申告書
(第二表)住民税・事業税に関する事項の寄付金税額控除(条例指定分)の欄に記入することで適用されます。
『所得控除』
寄付金額から2,000円を差引いた金額を課税所得から控除できます。減少する所得税額は課税所得に対応する税率によって異なります。
(例)寄付金が30,000円で課税所得が400万円(税率20%)の場合
税金の減少額: (30,000円-2,000円)×20%=5,600円
所得税が5,600円減少し、実質負担額は24,400円(30,000円-5,600円)となります。
この場合、税額控除を選択した方が税金の減少額は多くなります。
<寄付金控除の適用要件>
1 寄付した年の翌年の確定申告を行ってください。
2 岡崎学園が発行した寄付金受領書、特定公益増進法人であることの証明書(写)を確定申告書に添付してください。
3 税額控除を行う場合、所定の計算明細書の添付と特例適用条文等の記載が必要となります。
<ご注意>
1 優遇措置を受けられる寄付金額は総所得金額等(収入金額ではありません、所得控除差引き前の金額となります)の40%(住民税については
30%)までが対象となります。それを超える部分は控除の対象となりません。
2 税額控除は所得税額の25%を限度となりますので、寄付金額が多い場合、所得税額との関係で上記例に示した算式に基づく計算額よりも
税金の減少額が少なくなることがあります。また、税額控除よりも所得控除を選択した方が有利になることがあります。
3 寄付金控除に必要な「寄付金受領書」及び各「証明書(写)」は、学園に寄付が入金され次第お送りいたします。
法人が岡崎学園に寄付を行う場合、法人税法の寄付金の取扱いに基づき支出した事業年度の損金に算入することができます。損金算入の方法として、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類がありますが、「受配者指定寄付金」(※)の制度を利用することで指定寄附金として全額損金算入することができます。
(※) 日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)が私立学校の教育研究の発展に寄与するために寄付者(企業等)からの寄付を受け入れ、これを寄付者が指定した学校法人に配付するものです。事業団を通じての寄付となりますが、必ず岡崎学園に入金されます。
「特定益増進法人に対する寄付金」は一般寄付金とは別枠で特別損金算入限度額が設けられていますが、限度額があるため「受配者指定寄付金」の制度を利用したほうが有利となります。
『受配者指定寄付金』
優遇措置を受けるためには事業団宛に申込み手続が必要ですが、手続は学園が行います。損金算入の要件として事業団が発行する「寄付金受領書」が必要となります。学園を通して寄付者である企業等にお送りします。【受配者指定寄付金が法人税法上最も有利となっております。】
『特定公益増進法人に対する寄附金』
岡崎学園に直接寄付の手続(申込み及び振込等)を行っていただきます。損金算入の要件として、岡崎学園が発行した寄付金受領書、特定公益増進法人であることの証明書(写)が必要となります。
特別損金算入限度額:(所得金額×6.25/100 + 期末の資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000)×1/2